Basement Workshop
Miscellaneous stuff about audio, radios, guitar and alcohol
カテゴリー「チューナー」の記事一覧
- 2026.02.22
[PR]
- 2011.08.19
されどダイポール
- 2011.06.15
SONY ST-5000F (その 2)
- 2011.04.03
SONY ST-5000F
- 2011.01.18
TRiO KT-1100
- 2010.10.31
YAMAHA TX-900 その後
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
されどダイポール
(これまでの経緯と考察)
FM 用のアンテナとして、ヘンテナ、フォールデッドダイポール、J-Pole、MLA
と色々いじってきてみて、ぼんやりと感じていたことがやはり当たっていることが分かった。
(1) 300Ωフィーダなどの細い線を使用するとだめ (Folded Dipole、J-Pole で使用)
(2) 平衡アンテナを同軸で給電するには、バランを使用しないとアンテナの正確な特性が分からず、何を実験しているか分からなくなる。
(3) できれば、Q が大きい方が受信信号の品位が高くなる確率が高くなる。 しかし、Q が高いアンテナはゲインが低い (またはマイナス) ため、弱電界では実用的でない。
(1):アンテナの種類による違いではなく、恐らく表皮効果が顕著に現われて放射効率 (入射効率?) が悪くなっているのだろう。
FM チューナー付属のいわゆる T 型アンテナ (インピーダンスがアンマッチ*1) はこの部類に入る。
本来放射抵抗が約 75Ωのアンテナ(ダイポール)を、高々 1mm の細線でアンテナとフィーダ (インピーダンス不明*1) を構成し、300Ω端子に接続しているのだ。
*1: 仮にこのフィーダのインピーダンスが 150Ω であり、フィーダ部分の長さが目的周波数に対し 1/4λ + 1/2λ x n になっているとすれば正しい。 これは、Q マッチによる整合と見ると、75Ω/300Ω の整合が取れていることになる。 解説はここ。 さすがモガミ電線。
強度も理由ではあるが、メーカの八木宇田アンテナのラジエータ (Folded Dipole) 部分のパイプの太さは、放射効率向上のためでもある。
300Ωのフィーダで FM 帯域用フォールデッドダイポールを作り、300Ω平衡/75Ω不平衡のバラン経由で給電したが、ダメ。 結局 FM チューナー付属の T 型アンテナより安定度が若干ましなだけ。
(2):周囲の状況に影響されて動作が不安定。 準導体 (=人間) や金属の影響を強く受ける上に、指向性がぐちゃぐちゃ。
(3):改めて思い出すのは、アンテナはスカート特性が緩やかなバンドパスフィルタ (整数倍の高調波には同調するが) であるということ。 だから、FM 局ごとに同調し、Q が大きくかつ高ゲインのアンテナがあるとすれば、理想。
(今回の製作)
初心に戻るため、構造がシンプルなダイポールを直径 4mm のアルミパイプ 900mm x 2 で製作。 4mm も十分な直径とは思えないが、実験の容易性から選択。
このダイポールをシュペルトップバラン付きの75Ωケーブルで適当に鴨居にぶら下げてみて、驚き。
確かに信号強度は良いとはいえないが、何故か音質が良いのだ!
これは、市販のアルミパイプ製 4 エレメント八木のフォールデッドダイポール部分を単独で使用した時と同じ印象。
アンテナの材質で音質が変化しているという訳ではなく、
・表皮効果による効率低下が少ない
・平衡/不平衡の変換が完全 (同軸表皮に電流が流れない)
・SWRが低い (=インピーダンスマッチングが取れている)
ということにより、8 の字特性が綺麗で、不要な電波やノイズの影響を受けにくく、IMD が悪くならないからだろう。
前述した Q の高い指向性アンテナの基本形がダイポールということになる。
(将来の方向)
ダイポールのスタック
FM 用 MLA のスタック?(同調型。指向性は?)
トラップ付き八木のスタック?(トラップ付き=共振型=高 Q だが、VHF 用アンテナとして実用的なのか?)
FM 用のアンテナとして、ヘンテナ、フォールデッドダイポール、J-Pole、MLA
と色々いじってきてみて、ぼんやりと感じていたことがやはり当たっていることが分かった。
(1) 300Ωフィーダなどの細い線を使用するとだめ (Folded Dipole、J-Pole で使用)
(2) 平衡アンテナを同軸で給電するには、バランを使用しないとアンテナの正確な特性が分からず、何を実験しているか分からなくなる。
(3) できれば、Q が大きい方が受信信号の品位が高くなる確率が高くなる。 しかし、Q が高いアンテナはゲインが低い (またはマイナス) ため、弱電界では実用的でない。
(1):アンテナの種類による違いではなく、恐らく表皮効果が顕著に現われて放射効率 (入射効率?) が悪くなっているのだろう。
FM チューナー付属のいわゆる T 型アンテナ (
本来放射抵抗が約 75Ωのアンテナ(ダイポール)を、高々 1mm の細線でアンテナとフィーダ (
*1: 仮にこのフィーダのインピーダンスが 150Ω であり、フィーダ部分の長さが目的周波数に対し 1/4λ + 1/2λ x n になっているとすれば正しい。 これは、Q マッチによる整合と見ると、75Ω/300Ω の整合が取れていることになる。 解説はここ。 さすがモガミ電線。
強度も理由ではあるが、メーカの八木宇田アンテナのラジエータ (Folded Dipole) 部分のパイプの太さは、放射効率向上のためでもある。
300Ωのフィーダで FM 帯域用フォールデッドダイポールを作り、300Ω平衡/75Ω不平衡のバラン経由で給電したが、ダメ。 結局 FM チューナー付属の T 型アンテナより安定度が若干ましなだけ。
(2):周囲の状況に影響されて動作が不安定。 準導体 (=人間) や金属の影響を強く受ける上に、指向性がぐちゃぐちゃ。
(3):改めて思い出すのは、アンテナはスカート特性が緩やかなバンドパスフィルタ (整数倍の高調波には同調するが) であるということ。 だから、FM 局ごとに同調し、Q が大きくかつ高ゲインのアンテナがあるとすれば、理想。
(今回の製作)
初心に戻るため、構造がシンプルなダイポールを直径 4mm のアルミパイプ 900mm x 2 で製作。 4mm も十分な直径とは思えないが、実験の容易性から選択。
このダイポールをシュペルトップバラン付きの75Ωケーブルで適当に鴨居にぶら下げてみて、驚き。
確かに信号強度は良いとはいえないが、何故か音質が良いのだ!
これは、市販のアルミパイプ製 4 エレメント八木のフォールデッドダイポール部分を単独で使用した時と同じ印象。
アンテナの材質で音質が変化しているという訳ではなく、
・表皮効果による効率低下が少ない
・平衡/不平衡の変換が完全 (同軸表皮に電流が流れない)
・SWRが低い (=インピーダンスマッチングが取れている)
ということにより、8 の字特性が綺麗で、不要な電波やノイズの影響を受けにくく、IMD が悪くならないからだろう。
前述した Q の高い指向性アンテナの基本形がダイポールということになる。
(将来の方向)
ダイポールのスタック
FM 用 MLA のスタック?(同調型。指向性は?)
トラップ付き八木のスタック?(トラップ付き=共振型=高 Q だが、VHF 用アンテナとして実用的なのか?)
PR
SONY ST-5000F (その 2)
フロントパネルの文字は印刷ではなく彫り込んであるため消えにくいし、仮に消えても自分で修復が可能。
内部の各ユニットは個別にシールドされ、ユニット間の信号の飛び移りや外来ノイズに強い造りになっている。
(これまでの状態)
マルチプレクサと AF 段のバイパスコンデンサ、電源基板の 1 点のみ電解コンデンサを交換したが、電源電圧の 24V がトリマの調整範囲の上限一杯。 レギュレーションが悪くなっている証拠で、電源の残りのデカップリング用コンデンサの交換が必要と判断。
音もピークで歪が聞き取れる。
(今回の作業)
(1) クランプで固定してあるスナップイン型の電解コンの交換
オリジナルのクランプをそのまま流用するため、それぞれの直径 35mm (C601)、25mm (C604) に合ったものを購入。
ところが、25mm と表記のものは、実際は 22mm 程度でスカスカ。 スペーサを入れて対応。
2000uF/50V (C601): 2200uF/50V
2000uF/35V (C604): 3900uF/50V
(2) AF 段のカップリングコンデンサの交換
バイポーラやフィルムタイプも考えたが、普通のオーディオ用の電解コンとした。
1uF/12V (C527, C528): 1uF/50V
10uF/25V (C525, C526): 10uF/50V
(3) セパレーション調整用トリマの交換
R537 (5kΩ) をサーメットタイプ (コパル製) に交換。
(交換後の変化)
まず、無音時のノイズが若干減少。
数時間のエージングをするまでは音質に変化は感じられなかったが、それ以降、ピアノの重厚感やベースの音程感が十分に出るようになった。 未だに高音の抜けは良くないが、エネルギーバランスが良いので、不自然な感じは全くしない。
ピーク時の歪も感じられなくなり、非常に気持ちよい鳴りをするので、思わず聞きながら寝入ってしまったほど (笑)。
SONY ST-5000F
サブスピーカが 2m も離れた位置までぶっ飛んでいた以外は、オーディオ関係のダメージは無くて一安心したが、未だに音楽を長時間聴く気が起きない。
地震直前に落札した SONY ST-5000F がやっと届いたので、これで心のリハビリでも・・・。
(入手時の状態)
1971年で 10 万近いので、今に換算するととても買えないような価格。この年はラジカセを初めて買ってもらって喜んでいた時期なので、このような超高級機があったこと自体も知らなかった。
前オーナの取り扱いが丁寧だったのだろう、外観は非常に綺麗。とても 40 年前のものとは思えない。
削り出しのつまみの角が立っていて、新鮮。
「電源が入りません」 という説明だったが、電源が入らないのではなく、スケールのランプが暗いだけ(笑)。 問題なく音は出た。
チューニングを行うと、中から「キーキー」とダイアル用コードが軋む音。
ピークで歪むような感じがするが、ギターの胴鳴りが良く聞こえる。
(部品交換)
電解コンすべてを交換する必要があるが、今回は手持ちでできる部分のみ。
MPX基板: C511 (100uF/25V), C520 (100uF/25V) → 双方とも 220uF/35V に交換。
電源基板: C602 (220uF/50V) → 330uF/50V に交換。
(調整)
電源電圧調整 (12V/24V)
フロントエンドのLC (L101~L104, CT101~CT105)、IFT (IFT101) の調整。結果的にずれなし。
バンドの上側で若干表示ずれがあったので OSC のトリマコンデンサ (CT105) にて調整。
セパレーション (R537) を聴感で調整。
感度はこの時代の製品としては驚くほど良い。
ダイアルコードの鳴きは、取り回しを調整して解決。
(音質)
電解コン交換後のエージングも終わっていないし大きな期待はしていないが、低音が強調され、高音がストンと切れたような周波数特性。
ベースラインが良く聞こえ、ギターの胴鳴り、ピアノのスケール感が良く出る。
しかし、倍音の抜けが悪く、音場や楽器の実体が見渡せない。
レシオ検波の良い所は出ているが、部品の劣化によるものと思われる歪感が気になる。
これからの部品交換 (Tr/C/VR) による変化が楽しみ。
(サービスマニュアル)
ここ。
TRiO KT-1100
これまた懲りずに、今度は TRiO KT-1100。
SCA ノイズの取りきれない L-01T を改良した後継機がどのような鳴りをするのか興味津々だったのだ。
(外観と初期状態)
お。 トリオの無線機、9R-59DS/TS-520/820/830 を思い起こさせるボディーカラー。
写真で感じる大きさより小さい。
後部のネジ類に若干サビがあったり、汚れていた以外は問題なし。
FM の受信周波数が 2MHz もずれている。 AM がほとんど入感しない。
(調整と修理)
FM の周波数ズレは、OSC のトリマキャパシタを動かしても変化なし。 ここか。
4.7pF のセラミックコンデンサを OSC 用のバリコンに取り付けると、バッチリ動作するように。
この機種で使用されているトリマキャパシタは頻繁にダメになるようだが、マイグレーションが起きているのだろうか。
FM も AM も、フロントエンドの経年変化が酷い。 丁寧に何度も調整して、完全復活。
(肝心の音質)
おおお。 これが改良版のパルスカウント検波の音か。
何より音が派手で、ステレオ感 (セパレーション) が凄い。
L-01T で感じた、「PA を通したライブ感」 だ。 音の鮮度が素晴らしくいい。
・・・と、待てよ。 PLL 検波、レシオ検波との違いは?
PLL 検波で感じた、「冷たさ」 や 「暗さ」 は微塵も無い。
レシオ検波で感じる 「音場の広さ」 は無く、全部 「カブリツキ」 (笑)。
レシオ検波がコンサートホールの客席イメージなら、パルスカウント検波は、狭いライブ会場に行って、JBL/BOSE/RAMSA のスピーカの前で聴いている感じ。
PLL 検波が不得意な、ベースラインの音程感も問題なし。
え? では、レシオ検波よりいいのか?
全部聞こえる。 のに、PLL 検波と同様、楽器の実在感がない。
例えば、楽器の基音は左 CH から聞こえるが、その倍音は真ん中から聞こえる、といった具合。
エネルギーバランスもよく周波数特性も抜群に感じるが、左右のチャンネルの間にバラバラに鳴り、楽器の形が見えてこないのだ。
とは言え、自分の中の順位的には上位に食い込んだ感じ。
え? L-01T とどっちがいいのか? それは秘密 (笑)。
(サービスマニュアル)
ここ。
YAMAHA TX-900 その後
長い間熟成してきた (笑) TX-900、やっと重い腰を上げて修理することに。
その結果とは?
(これまでの経緯)
ステレオ信号の歪調整、T105/VR101、T106/VR102 を動かしても高調波のレベルが変化せず、おまけに不安定。
そればかりか、IFT のコアまで割ってしまい、TX-500 をドナーにするハメに。
(修理)
IFT の一次側のコイルにパラに入っているキャパシタの容量抜けが原因と思われた。
このため、0±60ppm / ℃ の温度特性の 9 pF の積層セラミックコンデンサを購入。
T105、T106 の一次側にパラに入れてみた。
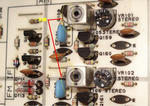
この結果、第二次高調波以降のレベルが IFT/VR の回転に同期して変化するようになり、調整完了!
(音質比較)
A/B 比較を瞬時にできるよう、 3 エレ八木と 4 エレ八木をスタックのように室内に設置 (笑)、リファレンスの CT-1000 と同時に動作させた。
YAMAHA + レシオ検波の特徴なのか音質がかなり近く、切り替えてもすぐに分からないくらい。
CT-1000 は音場が広く、鳥肌が立つような重低音が特徴だが、これに比し TX-900 は中低音域に膨らみがあり、超低音域はストンと切れている。
TX-900 は、楽器の一体感は若干弱い一方、さすがに S/N については CT-1000 のかなり上を行く。
もしかして、手持ちのシンセサイザー機の中では、一番かな。
やはり、楽器の鳴りとその一体感と言う意味では、レシオ検波が一番。
その結果とは?
(これまでの経緯)
ステレオ信号の歪調整、T105/VR101、T106/VR102 を動かしても高調波のレベルが変化せず、おまけに不安定。
そればかりか、IFT のコアまで割ってしまい、TX-500 をドナーにするハメに。
(修理)
IFT の一次側のコイルにパラに入っているキャパシタの容量抜けが原因と思われた。
このため、0±60ppm / ℃ の温度特性の 9 pF の積層セラミックコンデンサを購入。
T105、T106 の一次側にパラに入れてみた。
この結果、第二次高調波以降のレベルが IFT/VR の回転に同期して変化するようになり、調整完了!
(音質比較)
A/B 比較を瞬時にできるよう、 3 エレ八木と 4 エレ八木をスタックのように室内に設置 (笑)、リファレンスの CT-1000 と同時に動作させた。
YAMAHA + レシオ検波の特徴なのか音質がかなり近く、切り替えてもすぐに分からないくらい。
CT-1000 は音場が広く、鳥肌が立つような重低音が特徴だが、これに比し TX-900 は中低音域に膨らみがあり、超低音域はストンと切れている。
TX-900 は、楽器の一体感は若干弱い一方、さすがに S/N については CT-1000 のかなり上を行く。
もしかして、手持ちのシンセサイザー機の中では、一番かな。
やはり、楽器の鳴りとその一体感と言う意味では、レシオ検波が一番。
| 01 | 2026/02 | 03 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
[05/26 2H]
[02/03 ポムロル]
[01/24 cooltune]
[10/11 ポムロル]
[10/10 BLUESS]
[10/05 ポムロル]
[10/04 BLUESS]
(04/02)
(12/25)
(12/25)
(02/02)
(11/04)
(06/22)
(04/01)
(01/28)
(09/29)
(08/11)
HN:
ポムロル
性別:
男性
自己紹介:
真空管ラジオ、無線機、オーディオ、ギター、洋楽が大好きなオヤジ。
(10/04)
(10/05)
(10/07)
(10/07)
(10/18)
(10/21)
(11/10)
(11/28)
(12/24)
(12/25)


