Basement Workshop
Miscellaneous stuff about audio, radios, guitar and alcohol
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
SONY ST-S555ES
ST-J75の後継機、もしかしてSONY最後のレシオ検波の高級機。
本体側では電流出力、アンプの直前で電圧に変換という、変態好き(笑)にはたまらない手法。
レシオ検波のシンセサイザー機YAMAHAのTX-900もSONYのST-J75も太鼓判を押すまでには至らなかったので、期待していた。それに、ST-S555ESについての評判もTICを除くとさっぱり見つからないので、謎のモデルだったのだ。
(入手時の状態)
1年ほど前までは動作していたが、何も受信しなくなったという個体。
前々オーナが、RCA出力できるように改造している。
開けてみると、アブラとホコリとカビが山盛り(笑)。
電源SWのランプが切れていると思ったら、このモデルには最初から電源SWのランプは存在していない・・・。
(故障の状況)
アライメントがずれているというレベルのものでなく、バンドのどこでも何も受信しない。
フロントエンドへのCV(バラクタダイオードへの容量制御用の信号)を測りながらチューニングを上下させても、電圧に変化なし。
ここだ。
(トラブルシューティング)
Q602(2SC1362)のコレクタ電圧が低すぎ。
2SC1362に仕様の近い手持ちのTrに交換するも、変化なし。
ということは、Q601(2SK30GR)の故障か・・・。
部品の在庫から探し、Q601を交換すると、一発で動作。
(不可解な部品と動作)
Q601の交換で動作するようになったが、TP3での1.8Vへの調整を試みるも、RT601を回しても0.8Vのまま全く動かない。
基板上でRT601を測定すると、数100kΩを示す。1kΩのVRだから、パラレルに入る回路と合わせても1kΩ未満でなければいけない。
外して両端を計ると、無限大。そう、数MΩでもなく、どの端子間も無限大。
ところが、このRT601を交換すると、TP3の調整はできるようになったが動作しなくなったのだ!CVの電圧も30V近辺に張り付いたままチューニングに同期して変化しない・・・・。
交換したVRの足を上げて導通なしの状態にすると、何事も無かったように動作・・・。
設定周波数に対してリニアにVCを発生させられれば、各部の電圧が少々おかしくても、実際の回路が回路図と異なっても問題ないが、一体このRT601の位置付けは?
(その後の展開)
ネットで上記の不可解な動作を質問してみたら、「2SK30GRでなく2SK30を使ったのでは?」と回答あり。
大当たり。「手持ちで当座の修理」のミス。後でGRランクを購入して様子を見よう。
(その他の部品交換)
フロントエンド: C104/C106(100uF/16V)
コンポジット信号アンプ: C154/C155(220uF/16V)
MPX: C204/C205(470uF/16V)
AFアンプ: C218/C219(220uF/25V)
V-Iコンバータ: C223/C224(470uF/25V)
→C223の様子がおかしい。爆発(圧力解放弁の解放)はしていないようだが、電解液が上部に浸み出たような跡。外してみると、なんと側面に穴が!これまで、真空管ラジオのペーパコンが爆竹のように(笑)破裂したのを見たことがあるが、電解コンの側面破裂は初めて。一体、何が起きたのだろう?
(期待の音質-1)
す、凄い。電解コンの交換の影響がどの程度あるのか分からないが、奥行き感の表現と、聴感上のS/Nがいい。
ST-J75もS/Nがずば抜けていたが、このDNAをちゃんと引き継いでいるようだ。
BGMを鳴らしながらのアナウンサーの話も、「音楽は後ろ、声は前」の距離感が凄い。
見通しの良さは素晴らしいが、ボーカルの子音が若干きつい。
音が冷たい感じはSONYのPLL検波やKENWOODのパルスカウント検波の音に似ている。
低音の音離れも良くなく、ベースラインが余り追えないし楽器が見えてこない。エージング後に期待。
(期待の音質-2)
時間が経つにつれて、低音の不自然さと高音のきつさが取れてきた。
民放で音楽がかかっていなかったので、NHKのクラシックをかけたときのこと。楽器の「響き」とはこれだ ! と言わんばかりで、バイオリンは、弦ではなくボディが鳴っているのが分かる。
スピーカの裏側で楽器が鳴っているような実在感がある。
これまでシンセサイザー機に感じていた「息苦しさ」に対する嫌悪感もすっかり吹き飛び、只々脱帽。
これぞSleeper。
(ACT (Audio Current Ttransformer))
ACTケーブルの効果が知りたい。アンプ直前で電圧変換することにより、何か違いが感じられるのだろうか。
部品を手に入れたらケーブルを自作してその真価を試してみよう。
PR
無名インピーダンス変換法?
海外では有名な、同軸ケーブルを使用したインピーダンス変換手法の日本名が分からないでいる。
その名はTwelfth-Wave Transformer。
実体はQマッチの実用版、といったところなのだが、海外にはあって日本にはその呼び名が見つからない。
(Qマッチ)
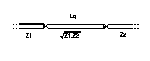
2つの異なるインピーダンスの伝送路の間に中間となるインピーダンスを挿入して変換するもの。
スタックアンテナのマッチングに同軸ケーブルを使用してマッチングをとるケースが一般に使用されている。
説明と簡単な計算機はここ。
ところが、単純に50Ωの同軸と75Ωの同軸を変換しようとすると、その中間のインピーダンスを同軸で簡単に構築できない。
(Twelfth-Wave Transformer)
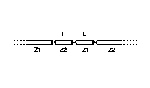
Qマッチでできない50Ωの同軸と75Ωの同軸の変換を、この手法を使用すると「50Ωの同軸と75Ωの同軸を使用して構築できる」のだ。
この変換部分に使用するそれぞれの同軸の長さ L がほぼ 1/12λ なのでこう呼ばれている。
詳細はここ。
(注意点)
フェライトコアを使用して構築するいわゆる「トランス」型のインピーダンス変換と異なり、目的周波数に対してのみ成り立つ変換器なので、注意を要する。
ただしある人物の実験では、特性が結構ブロードだという記述も見られる。
(お願い)
Twelfth-Wave Transformerに対する日本名をご存じの方がいらっしゃいましたら、どうぞ教えてください。
その名はTwelfth-Wave Transformer。
実体はQマッチの実用版、といったところなのだが、海外にはあって日本にはその呼び名が見つからない。
(Qマッチ)
2つの異なるインピーダンスの伝送路の間に中間となるインピーダンスを挿入して変換するもの。
スタックアンテナのマッチングに同軸ケーブルを使用してマッチングをとるケースが一般に使用されている。
説明と簡単な計算機はここ。
ところが、単純に50Ωの同軸と75Ωの同軸を変換しようとすると、その中間のインピーダンスを同軸で簡単に構築できない。
(Twelfth-Wave Transformer)
Qマッチでできない50Ωの同軸と75Ωの同軸の変換を、この手法を使用すると「50Ωの同軸と75Ωの同軸を使用して構築できる」のだ。
この変換部分に使用するそれぞれの同軸の長さ L がほぼ 1/12λ なのでこう呼ばれている。
詳細はここ。
(注意点)
フェライトコアを使用して構築するいわゆる「トランス」型のインピーダンス変換と異なり、目的周波数に対してのみ成り立つ変換器なので、注意を要する。
ただしある人物の実験では、特性が結構ブロードだという記述も見られる。
(お願い)
Twelfth-Wave Transformerに対する日本名をご存じの方がいらっしゃいましたら、どうぞ教えてください。
YAMAHA T-2 (その2)
でも、直った-!
(トライアンドエラーの顛末)
(1) TR407~TR410/2SC1917 の故障と思って交換 (2SC1917→2SC2240) してみたが、変化なし。
当たり前だ。 回路図を良く見ると、これらの Tr だけでなく、前段の差動アンプが故障していてもこの現象は起こるのだ。
(2) 前段のアンプは差動アンプ (2SA844 x 2) なので、hFE を揃えないと信号がプラス側とマイナス側で異なる増幅度になり、歪 (いびつ) になる。
測定用回路を組むのも暑くて面倒なので(笑)、思い切って hFE 測定機能の付属したテスターを購入。
さすがに、あっという間に測定とペア組が完了。 今回はとりあえず R チャンネルのみを交換。 と、ところが、変化なし・・・。
(3) 各部の電圧の比較をしてみたが、実はフィルタ部の L の抵抗値の測定をしていなかったことを思い出した。 なんと、一番最初に測定した L402 が無限大 (笑)。
やっと見つけた! 内部コイルの断線 (溶断) でなければ、コイルの末端とリード線の接合部が切れているだけかも。
と思って汚れた接合部にアンモニアを浸した綿棒をあててみると、緑色に・・・。 銅線が腐食して緑青になり、消滅した証拠。 復旧は不可能。
(当座の復旧)
L402 は 22mH (223J) というかなり大きなインダクタンス。
コリンズの無線機のレストアの時に必死で集めたコイルから近い値を探すが、最大でも 1mH か 2.2mH のものしかない。
ここは出力の周波数特性が若干乱れるだけと判断し、2.2mH の中で直流抵抗が近いものを採用。
(音出し)
まるで何事も無かったように一発で動作開始。
う~ん、音がいいぞ。
差動アンプ用 Tr を交換したせいなのか、フィルタの L を小さくしたせいなのか、R チャンネルの高音がすっきりとして抜けがいい。
(肝心の音質)
聴感上の周波数特性は低音が盛り上がった感じで、若干高音の抜けが悪い感じ (L ch) がする。
ただし、この低音が鳥肌もの。 分解能の高い低音、という言葉があるとすればこの音に当てはまる。
音程に揺らぎが全く無いだけでなく、ベースラインの動きが手に取るように分かる。
ギターのフィンガリングのノイズ、マイクへの息の被りなど演奏者の気配の再現が生々しい。
音場は、正に YAMAHA + レシオ検波のそれ。 CT-1000 ほど広さは感じないが、空気感とリバーブの心地よさが素晴らしい。
(今後の展開)
(1) L チャンネルの差動アンプを交換。
(2) L401/L402 を同じ値にする。 2.2mH の音も棄てがたいので、抜けの良さがこの値に起因するのであれば、採用する。
(3) TCA-1 の交換。 現状でもそれほど問題ないが、同調が外れているため信号強度が弱く、S/N が十分でない場合がある。
(4) 各部の調整。
YAMAHA T-2
当時のトップモデルで、C-2 とのペアを意図した超薄型のブラックフェイス。
その実力と音が知りたくて仕方がなかったが、今回やっと入手できた (やった-!)。
(当初の状態)
普通、「ジャンク」 と言っても 「未確認だからジャンク」 が多いが、今回は R チャンネルの音が出ない、本来のジャンク品。
ランプ切れもないし、キズもほとんど無し。 目盛が浮き上がるスケールとメータの照明が実に魅力的。
L チャンネルからしか音が出ないが、その音に何だかタダ者ではない凄みを感じる。
(簡略調整と結果)
ポインタがスケールに対し、500kHz ほどずれている。 TCO で調整。
入力感度が弱いため、フロントエンドを調整。
しかし、初段のアンテナ同調回路のトリマ TCA-1 だけは、回転させても変化なし。
信号強度が弱いのは、このトリマの故障により同調がとれないためと思われる。
回路図を見ても値が記入されていないが、数 pF~10pF だろう。
(トラブルシューティング)
POST AMP NA07061 基板上で正常に動作している L 側の TR407/TR409 各点の電圧を測定すると、R 側の TR408/TR410 の電圧と全く異なっている。 その他の TR/FET の測定電圧には L/R で差異が認められなかったので、この 2 点のどちらか (または双方) が故障の原因と思われる。 TR407~TR410/2SC1917 の交換が必要。
・・・ところが、2SC1917 なるトランジスタの情報が、ネット上にほとんど無い(泣)。
クロスリファレンスでは 2SC2390/2SC2240/2SC1844/2SC1344 ・・・と沢山候補が挙がっていたので、よく比較したのち交換しよう。
されどダイポール
(これまでの経緯と考察)
FM 用のアンテナとして、ヘンテナ、フォールデッドダイポール、J-Pole、MLA
と色々いじってきてみて、ぼんやりと感じていたことがやはり当たっていることが分かった。
(1) 300Ωフィーダなどの細い線を使用するとだめ (Folded Dipole、J-Pole で使用)
(2) 平衡アンテナを同軸で給電するには、バランを使用しないとアンテナの正確な特性が分からず、何を実験しているか分からなくなる。
(3) できれば、Q が大きい方が受信信号の品位が高くなる確率が高くなる。 しかし、Q が高いアンテナはゲインが低い (またはマイナス) ため、弱電界では実用的でない。
(1):アンテナの種類による違いではなく、恐らく表皮効果が顕著に現われて放射効率 (入射効率?) が悪くなっているのだろう。
FM チューナー付属のいわゆる T 型アンテナ (インピーダンスがアンマッチ*1) はこの部類に入る。
本来放射抵抗が約 75Ωのアンテナ(ダイポール)を、高々 1mm の細線でアンテナとフィーダ (インピーダンス不明*1) を構成し、300Ω端子に接続しているのだ。
*1: 仮にこのフィーダのインピーダンスが 150Ω であり、フィーダ部分の長さが目的周波数に対し 1/4λ + 1/2λ x n になっているとすれば正しい。 これは、Q マッチによる整合と見ると、75Ω/300Ω の整合が取れていることになる。 解説はここ。 さすがモガミ電線。
強度も理由ではあるが、メーカの八木宇田アンテナのラジエータ (Folded Dipole) 部分のパイプの太さは、放射効率向上のためでもある。
300Ωのフィーダで FM 帯域用フォールデッドダイポールを作り、300Ω平衡/75Ω不平衡のバラン経由で給電したが、ダメ。 結局 FM チューナー付属の T 型アンテナより安定度が若干ましなだけ。
(2):周囲の状況に影響されて動作が不安定。 準導体 (=人間) や金属の影響を強く受ける上に、指向性がぐちゃぐちゃ。
(3):改めて思い出すのは、アンテナはスカート特性が緩やかなバンドパスフィルタ (整数倍の高調波には同調するが) であるということ。 だから、FM 局ごとに同調し、Q が大きくかつ高ゲインのアンテナがあるとすれば、理想。
(今回の製作)
初心に戻るため、構造がシンプルなダイポールを直径 4mm のアルミパイプ 900mm x 2 で製作。 4mm も十分な直径とは思えないが、実験の容易性から選択。
このダイポールをシュペルトップバラン付きの75Ωケーブルで適当に鴨居にぶら下げてみて、驚き。
確かに信号強度は良いとはいえないが、何故か音質が良いのだ!
これは、市販のアルミパイプ製 4 エレメント八木のフォールデッドダイポール部分を単独で使用した時と同じ印象。
アンテナの材質で音質が変化しているという訳ではなく、
・表皮効果による効率低下が少ない
・平衡/不平衡の変換が完全 (同軸表皮に電流が流れない)
・SWRが低い (=インピーダンスマッチングが取れている)
ということにより、8 の字特性が綺麗で、不要な電波やノイズの影響を受けにくく、IMD が悪くならないからだろう。
前述した Q の高い指向性アンテナの基本形がダイポールということになる。
(将来の方向)
ダイポールのスタック
FM 用 MLA のスタック?(同調型。指向性は?)
トラップ付き八木のスタック?(トラップ付き=共振型=高 Q だが、VHF 用アンテナとして実用的なのか?)
FM 用のアンテナとして、ヘンテナ、フォールデッドダイポール、J-Pole、MLA
と色々いじってきてみて、ぼんやりと感じていたことがやはり当たっていることが分かった。
(1) 300Ωフィーダなどの細い線を使用するとだめ (Folded Dipole、J-Pole で使用)
(2) 平衡アンテナを同軸で給電するには、バランを使用しないとアンテナの正確な特性が分からず、何を実験しているか分からなくなる。
(3) できれば、Q が大きい方が受信信号の品位が高くなる確率が高くなる。 しかし、Q が高いアンテナはゲインが低い (またはマイナス) ため、弱電界では実用的でない。
(1):アンテナの種類による違いではなく、恐らく表皮効果が顕著に現われて放射効率 (入射効率?) が悪くなっているのだろう。
FM チューナー付属のいわゆる T 型アンテナ (
本来放射抵抗が約 75Ωのアンテナ(ダイポール)を、高々 1mm の細線でアンテナとフィーダ (
*1: 仮にこのフィーダのインピーダンスが 150Ω であり、フィーダ部分の長さが目的周波数に対し 1/4λ + 1/2λ x n になっているとすれば正しい。 これは、Q マッチによる整合と見ると、75Ω/300Ω の整合が取れていることになる。 解説はここ。 さすがモガミ電線。
強度も理由ではあるが、メーカの八木宇田アンテナのラジエータ (Folded Dipole) 部分のパイプの太さは、放射効率向上のためでもある。
300Ωのフィーダで FM 帯域用フォールデッドダイポールを作り、300Ω平衡/75Ω不平衡のバラン経由で給電したが、ダメ。 結局 FM チューナー付属の T 型アンテナより安定度が若干ましなだけ。
(2):周囲の状況に影響されて動作が不安定。 準導体 (=人間) や金属の影響を強く受ける上に、指向性がぐちゃぐちゃ。
(3):改めて思い出すのは、アンテナはスカート特性が緩やかなバンドパスフィルタ (整数倍の高調波には同調するが) であるということ。 だから、FM 局ごとに同調し、Q が大きくかつ高ゲインのアンテナがあるとすれば、理想。
(今回の製作)
初心に戻るため、構造がシンプルなダイポールを直径 4mm のアルミパイプ 900mm x 2 で製作。 4mm も十分な直径とは思えないが、実験の容易性から選択。
このダイポールをシュペルトップバラン付きの75Ωケーブルで適当に鴨居にぶら下げてみて、驚き。
確かに信号強度は良いとはいえないが、何故か音質が良いのだ!
これは、市販のアルミパイプ製 4 エレメント八木のフォールデッドダイポール部分を単独で使用した時と同じ印象。
アンテナの材質で音質が変化しているという訳ではなく、
・表皮効果による効率低下が少ない
・平衡/不平衡の変換が完全 (同軸表皮に電流が流れない)
・SWRが低い (=インピーダンスマッチングが取れている)
ということにより、8 の字特性が綺麗で、不要な電波やノイズの影響を受けにくく、IMD が悪くならないからだろう。
前述した Q の高い指向性アンテナの基本形がダイポールということになる。
(将来の方向)
ダイポールのスタック
FM 用 MLA のスタック?(同調型。指向性は?)
トラップ付き八木のスタック?(トラップ付き=共振型=高 Q だが、VHF 用アンテナとして実用的なのか?)
| 11 | 2025/12 | 01 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
[05/26 2H]
[02/03 ポムロル]
[01/24 cooltune]
[10/11 ポムロル]
[10/10 BLUESS]
[10/05 ポムロル]
[10/04 BLUESS]
(04/02)
(12/25)
(12/25)
(02/02)
(11/04)
(06/22)
(04/01)
(01/28)
(09/29)
(08/11)
HN:
ポムロル
性別:
男性
自己紹介:
真空管ラジオ、無線機、オーディオ、ギター、洋楽が大好きなオヤジ。
(10/04)
(10/05)
(10/07)
(10/07)
(10/18)
(10/21)
(11/10)
(11/28)
(12/24)
(12/25)


